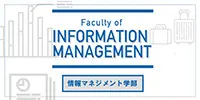君にすすめる一冊の本(WEB版)2024年度
紹介されている本はメディアセンターに所蔵していますので是非読んでみてください!
君にすすめる一冊の本(WEB版)2024年度
【推薦者】大久保利宏 先生(澳门皇冠体育_皇冠体育app-在线*投注)
*コメント*
私は学生の時、箱根駅伝大手町のゴールで毛布を広げて同級生のランナーを迎えたことがある。当時の箱根駅伝は、一般国道を学生の駆けっこで利用させていいのかという批判や、交通整理や警備の関係で廃止を求める声が強かった。テレビの全レースをテレビ中継することもなかった。
それが、今では視聴率が30%超し、沿道にはファンが押し寄せるというマンモスイベントに発展した。日本発祥であるEKIDENというスポーツ文化を知ることができる。
*コメント*
私は学生の時、箱根駅伝大手町のゴールで毛布を広げて同級生のランナーを迎えたことがある。当時の箱根駅伝は、一般国道を学生の駆けっこで利用させていいのかという批判や、交通整理や警備の関係で廃止を求める声が強かった。テレビの全レースをテレビ中継することもなかった。
それが、今では視聴率が30%超し、沿道にはファンが押し寄せるというマンモスイベントに発展した。日本発祥であるEKIDENというスポーツ文化を知ることができる。
【推薦者】小島憲明 氏(役員)
*コメント*
私たちの行動は、思いも寄らない何かに影響されている。
それは人間の先入観や偏見といった「勘違い」が原因となって現れる。それらの「認知バイアス」を紹介しながら、その現象を具体的に述べてる。例えば、銘柄を隠してコーラの飲み比べをすると、一番売れているコーラが必ずしも一番美味しいと評価されているわけではない。これらの「認知バイアス」を理解することで、人間の行動や、その裏にある科学の面白さを紹介している一冊である。
*コメント*
私たちの行動は、思いも寄らない何かに影響されている。
それは人間の先入観や偏見といった「勘違い」が原因となって現れる。それらの「認知バイアス」を紹介しながら、その現象を具体的に述べてる。例えば、銘柄を隠してコーラの飲み比べをすると、一番売れているコーラが必ずしも一番美味しいと評価されているわけではない。これらの「認知バイアス」を理解することで、人間の行動や、その裏にある科学の面白さを紹介している一冊である。
【推薦者】高岡正幸 氏(役員)
*コメント*
佐原高校同窓生から、友人が読売吉野作造賞を受賞した本だからといただいた。読んでみると、目からうろこであった。第一次対戦の前、アルゼンチンとチリは天然資源や農畜産品の輸出で、日本の倍以上のGDPを誇ったが、その後の恐慌や国策の失敗で凋落したことや、マレーシアが建国の際、極端に華僑やインド系を排除して国づくりをしたため、現在のシンガポールとの差になった話など。あのジョホール海峡を渡って水や食料をすべて輸入しているシンガポールにマレーシア人が毎日数十万人も海峡を渡り隣国に働きに行く様子が頭に浮かんだ。
*コメント*
佐原高校同窓生から、友人が読売吉野作造賞を受賞した本だからといただいた。読んでみると、目からうろこであった。第一次対戦の前、アルゼンチンとチリは天然資源や農畜産品の輸出で、日本の倍以上のGDPを誇ったが、その後の恐慌や国策の失敗で凋落したことや、マレーシアが建国の際、極端に華僑やインド系を排除して国づくりをしたため、現在のシンガポールとの差になった話など。あのジョホール海峡を渡って水や食料をすべて輸入しているシンガポールにマレーシア人が毎日数十万人も海峡を渡り隣国に働きに行く様子が頭に浮かんだ。
【推薦者】小島憲明 氏(役員)
*コメント*
中国進出に出遅れたトヨタを、奥田碩と豊田章男が社長の時代に、世界のトヨタにふさわしい確固たる拠点を作り上げた物語。
その陰には中国で生まれ育った日本人の服部悦雄がいた。服部は優秀な学生であったが、中国の「大躍進運動」「文化大革命」の時代に強制労働などの厳しい苦難を生き抜いた。戦後トヨタに入社し、中国語が堪能であったことから中国への進出の責任者となり、トヨタと中国の自動車会社の統廃合に尽力した。この服部の凄まじい生き方とその時代の中国の国内情勢が詳しく描かれた手ごたえのある一冊である。
*コメント*
中国進出に出遅れたトヨタを、奥田碩と豊田章男が社長の時代に、世界のトヨタにふさわしい確固たる拠点を作り上げた物語。
その陰には中国で生まれ育った日本人の服部悦雄がいた。服部は優秀な学生であったが、中国の「大躍進運動」「文化大革命」の時代に強制労働などの厳しい苦難を生き抜いた。戦後トヨタに入社し、中国語が堪能であったことから中国への進出の責任者となり、トヨタと中国の自動車会社の統廃合に尽力した。この服部の凄まじい生き方とその時代の中国の国内情勢が詳しく描かれた手ごたえのある一冊である。
【推薦者】向後秀明 先生(国際学部)
*コメント*
他者が自分のことをどう思っている(評価している)か、気になりますよね。SNSで自分の情報を発信して、それに対する様々な反応に一喜一憂する-そのようなことに多くの時間を使ってしまうことがあると思います。人間は常に「反応する」存在ですが、そのことで心身が疲弊してしまうというのは皮肉な結果です。
「感情を、上げもせず、下げもしない」、そんな考え方や生き方があるということを知るのも何かの役に立つかもしれません。
*コメント*
他者が自分のことをどう思っている(評価している)か、気になりますよね。SNSで自分の情報を発信して、それに対する様々な反応に一喜一憂する-そのようなことに多くの時間を使ってしまうことがあると思います。人間は常に「反応する」存在ですが、そのことで心身が疲弊してしまうというのは皮肉な結果です。
「感情を、上げもせず、下げもしない」、そんな考え方や生き方があるということを知るのも何かの役に立つかもしれません。